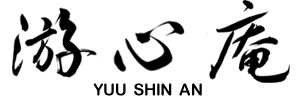数奇な旅を続けたその骨は、生まれ在所の種子島にある父母の墓の元に帰って来た。家督を継いだ実弟の喜びようは、尋常ではなかったという。
私は生きている頃、斉藤と呼ばれたこの男とは面識はなかった。最初の出会いはすでに骨となっていた。その骨と一緒に残されていた小さなショルダーバッグの中に納められていた手記がことの始まりであるである。それを読むことでその男にある種の近しさを覚えた。妻が所有する西荻のマンションの天袋に置かれていたその骨との突然の出会いは、驚きであった。
その部室は、私たち夫婦と親交のあった知人の石川にあいまいな形で貸していた。都内で用事があれば、いつでも私たちは、止まることができるということが唯一の取り決めであった。その石川が骨の所有者であった。浅からぬ縁があったのであろうと思った。
その後、ある夢を抱いて、部屋を出た石川は、天袋の奥にあったこの骨とショルダーバッグを置き忘れていたのだから、たいしたことはない。私が数ヶ月後このショルダーバッグから斉藤の手記を発見した。物書きが綴る獄中記だった。一気に読ませる肉声と筆力に圧倒された。私はなんだかこの獄中記の編集者になったような気分だった。種子島を出てからの歩みが短い文章から伝わる。私はこの獄中記から斎藤の人生の喜びと無念の世界に足を踏み入れた。
この獄中記、期間(刑期)はたった一年と二ヶ月と短いものであった。その間に大学ノート八冊には、独白する湯気が立ち昇っていた。ライターとしてのキャリアといくつかの著作もある人物だ。その著書名がなんと振るっているではないか。「悪魔のように生きてみないか」(笑)だという。もちろん私も、読んでみたが、題名ほどに刺激的ではなかった。獄中にあっても、出所後は、また頭を下げればライターとしてやっていけるという自信ものぞかせていた。
斉藤は、いったいなにを犯したのか?これがことの核心のはずがどうもあいまいで、しかも本人はいたって不本意な受刑者であると独白するのだ。その語り口は読む者を不安にさせた。その受刑生活が惨めで苦痛に満ちているのかというと、これまた不思議に明るいのだ。罪名は詐欺罪。他人から預かった絵を鑑定と称して、他者に再度預けてしまう。その結果が行方知れずという、お粗末かつ古典的な取り込み詐欺の中心に置かれていた。人間関係の細部に触れていないところが、手記とは言え、不安感に包まれる。斉藤自身は、加害者であり、被害者であると信じている。詐欺罪とは、刑法上も民法上も被害者による親告によって成立するもので、斉藤の論理展開からしても被害者A氏が斎藤を訴えるのは当然であったろうし、斉藤も自らの重大な過失を認めている。法理解釈からも、自らの有罪に対してある合理性を認めている。ただ自分の被害者としての立証と最終実行犯罪者への訴求は届かなかった。なんとも歯がゆいばかりなのだ。
余談になるが、その絵とは、百歳を過ぎても富士の姿を写し続けたあの日本画家のものだという。いつの時代も「美」と「醜」は混在していると感じた。
かくして、斉藤は、立派な罪人となり、獄に繋がれるのだ。二〇〇四年秋のことである。
この肉筆獄中記がなかなか読ませるのだ。流石は、現役の物書きだけある。ことの顛末から法曹界への批評、単に我身のえん罪に関することばかりではない。読書評があり、別れた妻子への恋慕の情、失くした友人仲間への詫びとうらみ、六十歳を過ぎての肉体の衰えと健康への不安が記されている。なぜか、明るい心持ちが見えてくる。
(以下、手記よりの引用)
「千葉刑務所から、ここ静岡に移送されここ数年来の腰痛が冬の寒さで悪化するのではと思っていたが、静岡は温暖の地で、空調設備も千葉より格段に良い。年齢への配慮からか、工場作業も軽微なものとしてくれている。健康診断もありがたい限りだ。なによりも図書室がいい」
そして、二〇〇六年冬 出所。
ここからは前述の石川と供に歩く旅であり、種子島へ帰り着くまでの謎解きの旅が続く。長崎県五島のたった三世帯しかない半泊集落を仮の棲み処としていた時にある一人の青年が現れた。
五島半泊から種子島への旅はこの続きとしよう。
瀬川正明(造園家として明圓寺の納骨堂・樹木葬「游心庵」のランドスケープに関わる。)
十五の春に庭師を志し いま八郷というムラに暮らす
この地が屍を晒す地になるのかもしれない
旅はただ漂い続けていればいいのに